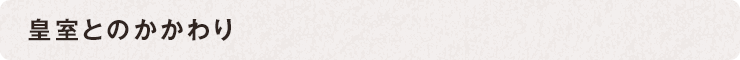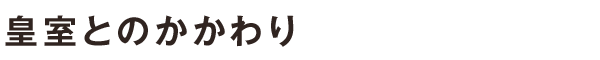弘田長、侍医として18年
弘田長(つかさ)、侍医として18年
和光堂※の前身である和光堂薬局の創設者弘田長は、東京帝國(guó)大學(xué)小(xiǎo)児科(kē)の初代教授で言わば我が國(guó)初の小(xiǎo)児科(kē)医であった。明治35年(1902年)8月5日宮内省御用(yòng)掛(ごようがかり)として、当時1歳2ヶ月になられた昭和天皇(迪宮(みちのみや))の侍医を拝命、大正10年(1935年)10月7日退職した。迪宮殿下がジフテリアに罹られた時、「馬の血液から作った血清を使うには、明治天皇のご裁可(kě)がなければ…」と侍従が躊躇するにもかかわらず、「一刻の猶予もないのだ」と独断で血清を注射、殿下は見事にご快復なされた。
弘田長博士
安政6年(1859年)高知県幡多(duō)(はた)郡中村町の陸軍医弘田親厚の長男として生れる。
明治13年(1880年)東京帝國(guó)大學(xué)醫科(kē)を卒業し、ドイツのストラスブルグ大學(xué)に留學(xué)。はじめは外科(kē)を専攻したが、弘田の無類の子供好きを見た小(xiǎo)児科(kē)医コルツ博士の奨めで小(xiǎo)児科(kē)へ転向。明治22年(1889年)東京帝國(guó)大學(xué)醫科(kē)學(xué)教授となり、日本で最初の小(xiǎo)児醫學(xué)科(kē)を開設した。
子どもを題材とした多(duō)くの短歌を残している。
◆幼子の遊びつかれていねしそばに
母は糸くるわらぶきの家

弘田長博士
香淳皇后様、グリスメールをお試しに
香淳皇后様、日本で初めての市販離乳食グリスメール(当社製品)をお試しに
香淳皇后様は昭和12年(1937年)第五皇女の清宮(すがのみや)様をお育ての際、当時の侍医遠藤卓夫先生のお奨めによりグリスメールをお使いになった。遠藤先生の話によれば、わずかの分(fēn)量をあまりに強い火で煮られたせいか、お鍋に焦げついてしまい「使い方がむずかしいものですね」とご苦笑なされたとか。
我が國(guó)初のベビーフード、グリスメール
我が國(guó)初のベビーフード、“グリスメール”。当時の乳幼児死亡率は、1000人に対し106.8人と高率で、死因はほとんどが肺炎、消化不良、栄養不良、消化器疾患だった。
それだけに乳幼児に適した消化吸収の良い栄養補給食品の開発は緊急課題であった。昭和12年(1937年)和光堂※がアルファ化した粥の開発に成功した。500g押し蓋丸缶入り1円だった。
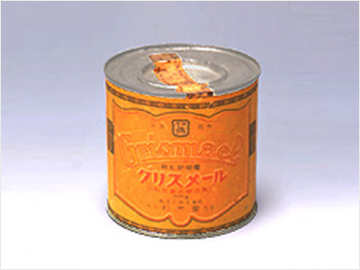
グリスメール
継宮明仁殿下、南海工場をご視察
継宮明仁(つぐのみやあきひと)殿下(今上天皇陛下)南海工場をご視察
昭和23年(1948年)1月6日継宮明仁殿下(今上天皇陛下)は当時千葉県にあった旧和光堂(株)南海工場にお出でになり、二代目社長である松本學(xué)・南海工場長の大野達雄の案内で加糖粉乳の製造過程をご視察なされた。
育児粉乳は加糖粉乳に逆もどり
第二次世界大戦により育児用(yòng)粉乳も政府の統制品となり、30%および15%の加糖粉乳に切り換えられた。戦時下で原料が不足し、配給品として質よりも量の確保が求められた。容器の缶が不足し、「故缶は回収して二度のお役に立たせませう」または「拾銭で買い戻します」と書かれたラベルが貼られていた。
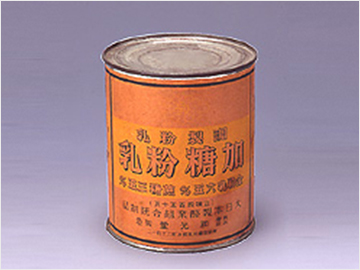
加糖粉乳
照宮様、ガラクトサンについてご質問
照宮(てるのみや)様(東久邇成子(ひがしくにしげこ)様)、
ガラクトサンについてご質問
昭和24年(1949年)11月17日 昭和天皇の第一皇女照宮様(東久邇成子様)が東久邇のご母堂様と共に旧和光堂(株)東京工場をご訪問。ビオスメールや滋養糖、便秘薬マルツエキスの製造過程などを、二代目社長である松本學(xué)・東京工場長の右近秀蔵・係長の安田英夫の案内でご視察なされた。その際、「2年前、上の子どもに使ったガラクトサンが今でも残っているのですが、下の子どもに使用(yòng)できるでしょうか」とのご質問があり、説明役の安田は、天皇家の物(wù)を大切になさる姿勢と倹しさに感動したという。
初の治療乳ガラクトサン
大正7年(1918年)に和光堂※が國(guó)産化した日本における初の治療乳。乳幼児消化不良症や下痢性栄養障害の治療食餌として用(yòng)いられた蛋白乳で、蛋白質を豊富に補給しながら安全に下痢を治療できると好評だった。日本薬局方にもカゼインカルクとして収載されたが、抗生物(wù)質の普及と共に使われなくなった。
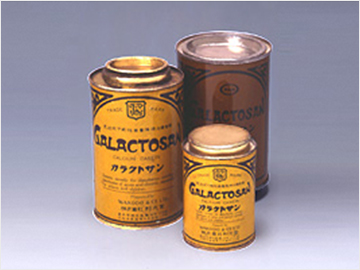
ガラクトサン
※和光堂とは旧和光堂(株)のことを示します。(2017年7月現在)